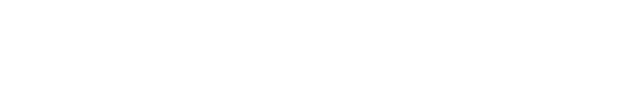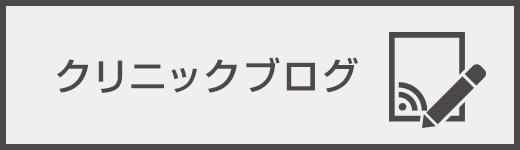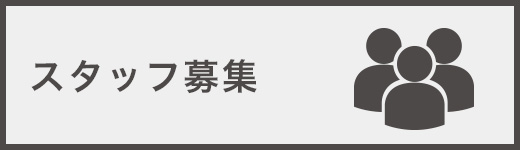睡眠外来(不眠症)のオンライン診療|不眠症でお悩みの方におすすめ!

夜なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚めてしまう、朝早くに目が覚めてしまうなど、不眠の悩みは深刻です。
多くの方が睡眠に関する悩みを抱えており、睡眠の質の低下は単に日中の眠気だけでなく、集中力の低下や気分の落ち込み、さらには長期的な健康リスクにも繋がりかねません。
もし不眠症や睡眠障害でお困りでしたら、一人で悩まずに専門の医療機関にご相談いただくことが、解決への第一歩です。
この記事では、そのために不眠症や睡眠障害についてや、当院のオンライン診療について解説しています。
【当院の睡眠薬料金】
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初月(お試し価格) | 2,980円 |
| 次月以降 | 9,680円 |
| 3ヶ月定期セット総額 | 22,340円 |
※LINE上での診療行為は連携先医療機関の一般社団法人徳志会の医師が担当します。
不眠症や睡眠障害でお困りなら睡眠薬がおすすめ

不眠症や睡眠障害にお悩みの方にとって、睡眠薬は有効な治療選択肢の一つです。
睡眠薬は医師の診断に基づいて処方される医療用医薬品で、なかなか眠れない、夜中に目が覚めてしまうといった症状の改善に役立ちます。
適切に使用することで、睡眠の質を向上させ、日中の生活の質も高めることが期待できます。
睡眠薬は入眠障害や中途覚醒といった症状を改善する医療用医薬品
睡眠薬は、不眠症の様々な症状に対して効果を発揮する医療用医薬品です。
寝床に入ってもなかなか眠れない入眠障害や、夜中に何度も目が覚めてしまう中途覚醒、朝早くに目が覚めてしまう早朝覚醒など、それぞれの症状に合わせた薬が処方されます。
睡眠薬は医師の診断に基づいて処方されるため、患者様の症状や体質に適したものが選ばれます。
自己判断での使用は避け、必ず医療機関を受診して適切な治療を受けることが大切です。
継続して服用することで睡眠の質の向上をサポート
睡眠薬は、継続的に適切に服用することで、より良い睡眠習慣の確立をサポートします。
一時的な効果だけでなく、規則正しい睡眠リズムを取り戻すことで、長期的な睡眠の質の向上が期待できます。
継続服用による効果は以下のようなものがあります。
- 睡眠リズムの安定化により、自然な眠気が訪れやすくなる
- 熟睡感が得られ、朝の目覚めが良くなる
- 日中の集中力や活動性が向上する
- 不眠への不安が軽減され、心理的な負担が減る
ただし、睡眠薬を継続して使用する場合は、医師との定期的な相談が欠かせません。
症状の改善状況を確認しながら、適切な服用期間や減薬のタイミングについて相談していくことが重要です。
当院では、患者様一人ひとりの状態に合わせて、治療計画をご提案いたします。
そもそも不眠症・睡眠障害とは?
不眠症とは、眠りたいという意思があるにもかかわらず、なかなか眠れない、夜中に目が覚める、朝早くに目が覚めるといった症状が現れ、その結果として日中の活動に支障をきたす状態を指します。
単に睡眠時間が短いだけでなく、日中に疲労感や集中力の低下などの影響が出ているかが重要なポイントです。
入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒・熟眠障害の4つに分類
不眠症の症状は、主に4つのタイプに分けられます。
ご自身の症状がどれに当てはまるか確認してみましょう。
| 不眠症のタイプ | 主な特徴 | 関連しやすい要因の例 |
|---|---|---|
| 入眠障害 | 寝床に入ってもなかなか寝付けない状態で、寝つくまでに30分から2時間以上かかる | ストレス、不安、緊張 |
| 中途覚醒 | 夜中に何度も目が覚め、一度起きるとなかなか再び寝付けない | 加齢、特定の身体疾患、ストレス |
| 早朝覚醒 | 普段より2時間以上早く目が覚めてしまい、その後眠れなくなる | 加齢に伴う体内時計の変化、うつ病 |
| 熟眠障害 | 睡眠時間は足りているはずなのに、ぐっすり眠った感じが得られない | 睡眠時無呼吸症候群、うつ病、ストレス |
これらの症状は単独で現れることもあれば、複数のタイプが組み合わさって現れることもあります。
例えば、入眠障害と中途覚醒の両方を経験する方も少なくありません。
各タイプの詳しい特徴について説明します。
- 入眠障害は精神的な問題や不安、緊張が強い時に起こりやすく、ストレスと深く関連しています
- 中途覚醒は高齢になるにつれて現れやすくなる傾向があり、夜中に2回以上目が覚める状態を指します
- 早朝覚醒は特に高齢の方で多く見られ、体内時計のリズムが前方にずれることで起こります
- 熟眠障害は朝起きても疲れが取れていない状態で、他の睡眠障害が隠れている場合があります
これらのタイプを把握することで、ご自身が抱える問題が医療の対象となる症状であることを認識しやすくなり、適切な治療への第一歩となります。
不眠が週3日以上、3ヶ月以上持続する場合は注意が必要
一時的な不眠は誰にでも起こり得ますが、症状の頻度と持続期間によって診断が変わります。
不眠の症状と、それに伴う日中の不調が週に3日以上あり、それが3ヶ月以上続く場合は「慢性不眠症」と診断される可能性*があります。 不眠症の診断基準を以下にまとめました。
| 診断の種類 | 診断基準 |
|---|---|
| 慢性不眠症 | 不眠症状が週3日以上、3ヶ月以上持続し、日中の機能障害を伴う |
| 短期不眠症 | 不眠症状が週3日以上、3ヶ月未満持続し、日中の機能障害を伴う |
重要なのは、夜間の睡眠の問題だけでなく、日中の活動にどれだけ支障が出ているかという点です。
以下のような日中の症状が見られる場合は、専門医への相談を検討しましょう。
- 日中の強い眠気や疲労感
- 集中力や記憶力の低下
- 気分の落ち込みやイライラ
- 仕事や学業の効率低下
- 対人関係への影響
これらの症状が続いている場合は、単なる睡眠不足ではなく、治療が必要な不眠症の可能性があります。
早めの相談が症状改善への近道となります。
不眠症・睡眠障害の原因は主に4種類

不眠症や睡眠障害の原因は多岐にわたりますが、大きく分けると心理的要因、生活習慣の乱れ、身体的要因、環境的要因の4つが挙げられます。
これらの要因が複雑に絡み合って不眠を引き起こしている場合も少なくありません。
不眠症・睡眠障害の原因①心理的要因
ストレス、不安、抑うつ、心配事といった心理的な要因は、不眠の大きな原因となります。
このような精神状態は脳を覚醒させやすく、リラックスして眠りにつくことを妨げます。
心理的要因による不眠の具体例をご紹介します。
- 仕事や人間関係でのストレス
- 将来への不安や心配事
- 重要な試験や面接前の緊張
- 家族や健康に関する悩み
- うつ病や不安障害などの精神的な病気
特に、精神的なストレスが睡眠に影響を与えるケースが多く見られます。
心理的要因が原因の場合、ストレスの軽減や心理的なサポートとともに、睡眠薬による治療が効果的な場合があります。
不眠症・睡眠障害の原因②生活習慣の乱れ
日常生活の中での様々な習慣が、体内時計を乱し、不眠を引き起こす原因となることがあります。
生活リズムの改善により、不眠症状が大幅に改善する場合も多くあります。
生活習慣による不眠の原因として、以下のようなものが挙げられます。
- 不規則な睡眠時間(交代勤務や時差ぼけなど)
- カフェインやアルコールの過剰摂取
- 就寝前の喫煙
- 運動不足または就寝直前の激しい運動
- 長すぎる昼寝や遅い時間の昼寝
- 寝床で睡眠以外の活動(仕事やスマートフォンの使用など)
これらの生活習慣は、体内時計のリズムを乱したり、脳を覚醒状態に保ったりすることで、質の良い睡眠を妨げます。
生活習慣の見直しは、睡眠薬による治療と併せて行うことで、より効果的な改善が期待できます。
不眠症・睡眠障害の原因③身体的要因
様々な身体的な病気や服用している薬の副作用が、不眠を引き起こすことがあります。
これらの要因を見逃すと、適切な治療ができない場合があるため、詳しい問診が重要となります。
身体的要因による不眠の原因を以下の表でまとめました。
| 要因の種類 | 具体例 | 睡眠への影響 |
|---|---|---|
| 身体の痛み | 関節リウマチ、腰痛、肩こりなど | 痛みにより寝つきが悪くなる、夜中に目が覚める |
| 呼吸器疾患 | 咳、喘息発作、睡眠時無呼吸症候群など | 呼吸困難により睡眠が妨げられる |
| 循環器疾患 | 心臓病、高血圧など | 動悸や息苦しさで睡眠が浅くなる |
| その他の疾患 | 腎臓病、糖尿病、前立腺肥大、アレルギー疾患など | 頻尿、かゆみなどで睡眠が中断される |
| 薬の副作用 | 降圧剤、甲状腺製剤、抗がん剤など | 薬の作用により不眠が生じる |
また、睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)といった、他の睡眠障害が不眠の症状を引き起こしている場合も少なくありません。
これらの場合、不眠症の治療だけでなく、原因となる睡眠障害自体の治療が必要となります。
不眠症・睡眠障害の原因④環境的要因
睡眠環境の問題も不眠の重要な原因となります。
快適な睡眠環境を整えることは、質の高い睡眠を得るための基本的な対策です。
環境的要因による不眠の原因として、以下のようなものがあります。
- 寝室の騒音(交通音、隣人の生活音、家族のいびきなど)
- 明るすぎる照明(街灯、電子機器のライトなど)
- 不快な室温や湿度(暑すぎる、寒すぎる、湿度が高い・低い)
- 体に合わない寝具(マットレスや枕の硬さ、高さなど)
- 慣れない環境(旅行先、引っ越し後など)
環境的要因は比較的改善しやすい要因でもあります。
寝室の温度を適切に保つ、遮光カーテンを使用する、自分に合った寝具を選ぶなどの対策により、睡眠の質を大幅に改善できる場合があります。
睡眠薬による治療と併せて、睡眠環境の見直しも行うことをおすすめします。
※LINE上での診療行為は連携先医療機関の一般社団法人徳志会の医師が担当します。
当院で処方している睡眠薬(デエビゴ)について

画像引用:エーザイ株式会社
当院では、睡眠薬として「デエビゴ」を処方しております。
デエビゴは従来の睡眠薬とは異なる作用機序を持つ睡眠薬で、依存性や翌朝への持ち越しといった副作用が比較的少ないとされています。
デエビゴの服用で期待できる効果
デエビゴは、脳内で覚醒を維持する物質であるオレキシンの働きを抑えることで、脳を覚醒状態から睡眠状態へと移行させ、自然な眠りを促す睡眠薬(オレキシン受容体拮抗薬)です。
デエビゴの服用により、以下のような効果が期待できます。
- 入眠のサポート
└ 寝つきを良くする効果があります - 睡眠維持のサポート
└ 夜間の睡眠を持続させ、途中で目が覚めることを減らす効果が期待できます - 睡眠の質の向上
└ より深く、質の高い睡眠の手助けをします
デエビゴは、入眠障害と中途覚醒の両方に有効性が示されています。
「自然な眠気」を誘発するという特徴は、従来の睡眠薬に対して抵抗感がある患者様にとっても受け入れやすいでしょう。
従来の睡眠薬が脳全体の活動を抑制するのに対し、デエビゴは覚醒を維持する特定の物質の働きを抑えるため、より自然な睡眠に近い状態を作り出すことができます。
デエビゴの副作用
デエビゴの主な副作用として報告されているものには、以下のようなものがあります。
副作用の現れ方には個人差があるため、気になる症状が出た場合は自己判断せず、必ず医師にご相談ください。
主な副作用の詳細を以下にまとめました。
| 副作用 | 詳細と対処法 |
|---|---|
| 眠気 | 最も多く報告されている副作用です。(10.7%)翌朝に眠気が残ることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。 |
| 頭痛 | 比較的多く見られる副作用です。(4.2%)症状が続く場合は医師にご相談ください。 |
| 倦怠感 | 日中の活動に支障が出る場合は医師と相談しましょう(3.1%) |
| 悪夢・異常な夢 | 睡眠のパターンに影響するため、夢の内容が変化したり、悪夢を見たりすることがあります。 |
| 睡眠時麻痺 | まれに報告されることがあります(金縛りのような状態) |
| 体重増加 | 食欲亢進を伴う体重増加が報告されることがあります。 |
参考:https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00068463
特に注意が必要なケースとして、以下の点にご注意ください。
- アルコールとの併用
└ 絶対に避けてください。デエビゴの効果が過剰に強まり、危険な状態になる可能性があります - ナルコレプシーまたはカタプレキシーのある方
└ 症状を悪化させる可能性があるため、デエビゴの服用はできません - 重度の肝機能障害のある方
└ 服用できません - 高齢者の方
└ 転倒のリスクなどを考慮し、慎重に投与します - 妊娠中・授乳中の方
└ 原則として服用は避けるべきとされています
副作用への対処法としては、服用タイミングや用量の調整、リラクゼーション法の導入などがありますが、いずれも医師との相談が不可欠です。
デエビゴと他の睡眠薬の違い
デエビゴは、従来の睡眠薬、特にベンゾジアゼピン系薬剤とはいくつかの重要な違いがあります。
これらの違いを理解することで、より適切な治療選択が可能となります。
| 特徴 | デエビゴ (オレキシン受容体拮抗薬) |
従来の睡眠薬 (例:ベンゾジアゼピン系) |
|---|---|---|
| 作用機序 | 脳の覚醒を維持するオレキシンをブロックし、自然な眠りを促す | GABA受容体に作用し、脳全体の活動を抑制する |
| 依存性リスク | 比較的低いとされる | 長期使用で依存形成のリスクあり |
| 持ち越し効果 | 比較的少ないとされるが、傾眠はあり得る | 薬剤により翌朝への眠気やふらつきが残りやすい場合がある |
| 筋弛緩作用 | ほとんどないとされる(転倒リスク低減) | 筋弛緩作用があり、特に高齢者では転倒のリスクあり |
| 離脱症状 | 比較的起こりにくいとされる | 急な中断で離脱症状(反跳性不眠など)が起こることがある |
デエビゴの「依存性が低い」「筋弛緩作用がほとんどない」という特徴は、睡眠薬治療に不安を感じる患者様にとって大きなメリットとなります。
また、同じオレキシン受容体拮抗薬であるベルソムラと比較すると、デエビゴはオレキシン受容体への結合が速く、離れるのも速いため、寝つきの改善効果と持ち越し効果の少なさのバランスが良いとされています。
ただし、デエビゴの血中半減期は比較的長いものの、オレキシン受容体拮抗薬の場合、この半減期の長さが必ずしも翌朝の眠気の強さと直結するわけではありません。
※LINE上での診療行為は連携先医療機関の一般社団法人徳志会の医師が担当します。
デエビゴの効果期間について

デエビゴの効果が現れるまでの時間や、治療期間の目安は、患者様の状態や体質によって異なります。
一般的には、服用後比較的速やかに効果が現れることが多いですが、効果を実感するまでには数日かかる場合もあります。
治療期間については、症状の改善度合いを見ながら医師と相談して決めていくことが大切です。
自己判断で服用を中止したり、量を調整したりすることは避けましょう。
デエビゴを服用してから効果が出るまでの目安
デエビゴは、一般的に服用後約30分程度で効果が現れ始めるとされています。
血中濃度が最も高くなるのは服用後約1時間です。
そのため、就寝直前に服用することが推奨されています。
デエビゴの効果発現について、以下の表で詳しくご説明します。
| 時間 | 効果の状況 |
|---|---|
| 服用後30分 | 効果が現れ始める時間の目安 |
| 服用後1時間 | 血中濃度が最も高くなり、効果がピークに達する |
| 服用後数時間 | 睡眠維持効果が持続し、夜間の覚醒を抑制 |
効果的な服用のために、以下のポイントにご注意ください。
- 就寝直前に服用する
└ 効果が現れる時間を考慮し、床に就く直前に服用しましょう - 空腹時の服用が望ましい
└ 食事と同時、または食直後に服用すると、薬の吸収が遅れて効果発現が遅れる可能性があります - 服用後はすぐに床に就く
└ 効果が現れ始めてから活動を続けると、転倒などの危険があります - アルコールは絶対に避ける
└ 効果が過剰に強まり、危険な状態になる可能性があります
個人差により効果の現れ方が異なる場合がありますので、服用開始後は医師と相談しながら服用タイミングを見つけていくことが重要です。
デエビゴでの治療期間の目安
デエビゴによる治療期間は、個々の患者様の症状や改善度によって大きく異なります。
治療期間の段階的な目安を以下の表でご紹介します。
| 治療段階 | 期間の目安 | 治療の内容 |
|---|---|---|
| 導入期 | 服用開始から1~2週間 | 効果や副作用の確認、用量調整 |
| 安定期 | 1ヶ月~数ヶ月 | 症状の改善維持、生活習慣改善の併用 |
| 減薬・中止期 | 症状改善後 | 段階的な減薬、睡眠習慣の自立に向けた調整 |
生活習慣の改善などと並行して治療を進め、医師と相談しながら減薬や中止を検討していくことになります。
治療期間については、患者様一人ひとりの状況に合わせて柔軟に対応いたしますので、不安な点があれば遠慮なく医師にご相談ください。
当院のデエビゴ料金
当院のオンライン診療でデエビゴの処方を受ける場合の費用についてご説明します。
患者様にとって分かりやすく、継続しやすい料金体系を設けており、初回はお試し価格でご利用いただけます。
以下が当院でのデエビゴ処方料金です。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初月(お試し価格) | 2,980円 |
| 次月以降 | 9,680円 |
| 3ヶ月定期セット総額 | 22,340円 |
初月のお試し価格は、初めてデエビゴを服用される方が安心して治療を始められるよう設定しています。
この期間中に効果や副作用を確認していただき、継続的な治療について医師と相談していただけます。
3ヶ月定期セットをご利用いただくと、単月でのお支払いよりもお得になる料金設定です。
※LINE上での診療行為は連携先医療機関の一般社団法人徳志会の医師が担当します。
睡眠の質を高める方法|自分でできる対策について

睡眠薬による治療と並行して、ご自身でできる対策(睡眠衛生の改善)を行うことも、睡眠の質の向上には非常に重要です。
規則正しい生活を送る、寝室の環境を整える、リラックスできる就寝前の習慣を取り入れるなど、日々の生活の中で意識できることはたくさんあります。
これらの対策を実践することで、睡眠薬の効果を高め、より質の高い睡眠を得ることが期待できます。
就寝時間と起床時間を整える
毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計が整い、自然な眠気が訪れやすくなります。
特に、休日に寝だめをすると体内時計が乱れる原因になるため、平日も休日もできるだけ同じ時刻に起きることが重要です。
規則正しい睡眠リズムを作るためのポイントをご紹介します。
- 毎日同じ時刻に就寝し、同じ時刻に起床する
- 休日も平日と同じ起床時刻を心がける
- 朝起きたら太陽の光を浴びて体内時計をリセットする
- 夜更かしした翌日も、いつもの時刻に起床する
- 眠くなってから床に就き、眠れない時は一度寝床から出る
昼寝をする場合の注意点についても把握しておきましょう。
| 昼寝のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 時間帯 | 午後3時より前に行う(それ以降は夜の睡眠に影響する可能性があります) |
| 長さ | 20~30分程度にとどめる(長すぎると深い眠りに入り、目覚めが悪くなります) |
| 環境 | 暗すぎない場所で、軽く横になる程度にする |
「8時間眠らなければならない」といった思い込みはかえって睡眠への不安を高めることがあるため、
日中の眠気で困らなければ睡眠時間は十分と捉え、時間にこだわりすぎないことも大切です。
適度な運動で眠りやすくする
日中に適度な運動を行う習慣は、熟睡を促します。
運動により体温が上昇し、その後体温が下がることで眠気が誘発されるため、質の良い睡眠につながります。
具体的には、以下のような運動を取り入れてみましょう。
- ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動がおすすめです
- 運動は日中や夕方早めに行うのが理想です
- 週に3~4回、30分程度の運動を継続することで効果が期待できます
- 激しすぎる運動は逆効果になる場合があるため、心地よい疲労感を得られる程度にしましょう
ただし、就寝直前の激しい運動は体を興奮させてしまうため、避けるようにしましょう。
就寝前にはストレッチや軽いヨガなど、リラックス効果のある軽い運動がおすすめです。
寝る前はPCやスマホを触らないようにする
パソコンやスマートフォン、テレビなどの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、寝つきを悪くします。
ブルーライトが睡眠に与える影響と対策をご紹介します。
- 就寝1~2時間前からはパソコン、スマートフォン、テレビの使用を控える
- 寝室にスマートフォンを持ち込まない、または画面を下向きにして置く
- ブルーライトカット機能を活用する(夜間モード、ナイトシフトなど)
- 寝室の照明も明るすぎないものに調整する
- 読書をする場合は、電子書籍ではなく紙の本を選ぶ
また、就寝1~2時間前にぬるめのお湯(38~40℃程度)での入浴も、心身をリラックスさせ、寝つきを良くする効果があります。
入浴により一時的に体温が上がり、その後体温が下がることで自然な眠気が誘発されます。
これらの生活習慣の改善は、睡眠薬による治療と併用することで、より効果的な不眠症の改善が期待できます。
継続することが重要ですので、無理のない範囲から始めて、徐々に習慣として定着させていきましょう。
睡眠外来についてよくある質問
睡眠外来を受診するにあたって、様々な疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、患者様からよくいただくご質問とその回答をご紹介します。
治療に対する不安や疑問を解消していただき、安心して睡眠外来を受診していただけるよう、詳しくお答えいたします。
不眠症や睡眠障害は治りますか?
多くの場合、不眠症や睡眠障害は適切な治療と生活習慣の見直しによって改善が期待できます。
「一生治らない」と諦める必要はありません。
完全に治癒するケースもあれば、症状が大幅に軽減され、日常生活に支障がなくなるケースも多くあります。
治療期間は原因や重症度によって異なりますが、数回の通院で改善する方もいらっしゃいます。
睡眠外来に相談すべきタイミングはどのような時ですか?
不眠の症状が週に3日以上あり、それが3ヶ月以上続いている場合や、不眠によって日中の倦怠感、集中力低下、気分の落ち込みなど、日常生活に支障が出ている場合は相談をおすすめします。
また、ご自身で生活習慣の改善などを試みても改善しない場合や、いびきがひどい、睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された場合なども相談のタイミングです。
不眠症や睡眠外来は睡眠薬での治療のみですか?
睡眠薬による治療だけではありません。
しかし、当院はオンライン診療ということもあり、睡眠薬での治療を行っております。
睡眠障害でお困りならまずは当院のオンライン診療まで
不眠症や睡眠障害は、決して我慢するものではありません。
当院では、お忙しい方や様々な理由で通院が難しい方でも、ご自宅にいながら気軽に専門医の診察やデエビゴの処方を受けることができるオンライン診療を提供しております。
もし不眠のことでお悩みなら、どうぞ一人で抱え込まず、まずは当院のオンライン診療までお気軽にご相談ください。
※LINE上での診療行為は連携先医療機関の一般社団法人徳志会の医師が担当します。